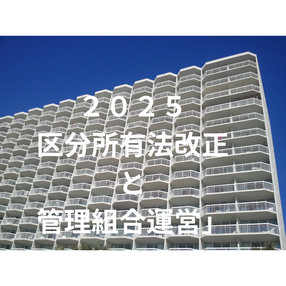
今回の改正では、所在不明者や総会において議決権行使をしない人は、除外することができる仕組みが導入される。
建替え決議などは、4/5以上の賛成を必要とする。この場合、所在不明者や議決権を行使しない人は反対者として扱うことになっている。
例えば100名中79名が賛成でも、建替え議案は否決される。極端な話、残り21名が所在不明者であったり、マンション管理に無関心のため議決権を行使しなかった場合でも、議案は否決される。
このような状況を改善すべく、区分所有法が見直された。
所在不明者の除外規定
所在等が不明な区分所有者について、裁判所による除外認定を受ければ、建替え決議などの区分所有権の処分を含めて全ての決議を対象に決議の母数から除外できることとなった。
これにより所在不明者がいる場合の管理の円滑化が図られる。特に、例えば戸数20戸や30戸の小規模マンションにおいては、効果が大きい。
出席者多数決制度
区分所有者の高齢化、死亡・相続放棄、管理組合活動に無関心な者の増加、投資目的の区分所有者などにおいて、集会における議決権行使をしない者が相当数ある。
管理規約の変更など3/4以上の賛成を必要とする特別決議において議決権行使をしない者を反対者として取り扱われて議案が否決されるという状況が多々あった。
そこで下記の議案においては、委任状や議決権行使書提出者も含む出席者の多数(過半数や3/4以上など)で決議するという制度が導入された。
①普通決議
②共用部分の変更
③復旧決議
④規約の設定・変更・廃止の決議
⑤管理組合法人の設立・解散の決議
⑥義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求、区分所有権などの競売請求及び専有部分の引き渡し等の請求
⑦管理組合法人による区分所有権等の取得の決議
なお、集会成立の定足数については、②から⑦に関しては、法律で過半数とするようになった。
①に関しては、集会成立の定足数を定めないことになった。
但し、現状の標準管理規約では定足数を過半数として、出席者の過半数で決議できるように定められており、これを採用しているケースが多い。
これにより、組合員・議決権の総数の4/5以上、3/4以上、過半数などの賛成が必要であったものが、
出席者、委任状や議決権行使書提出者の4/5以上、3/4以上、過半数などの賛成があれば、決議できるようになった。
総会運営の円滑化
今回の改正で、所在不明者を除外することができたり、議決権を行使しない人を除いた出席者多数決制度が導入され、総会の運営が格段に円滑化することが期待される。


コメントをお書きください